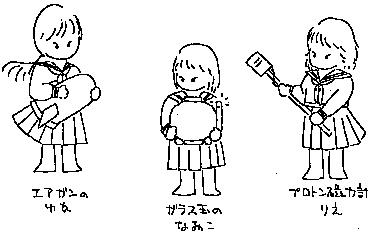きせる乗車の日本文化 鶴見俊輔
青磁社通信vol.9~エッセイ~
昭和二十四年四月一日から、私は、京都大学につとめた。
私は小学校卒業で日本の学歴を終えているので、日本の学校とはつながりがなく、友達は少ない。京都に移ってきても、土曜と日曜は行き場がなかった。
そういうとき、私を自宅にさそったり、外食にさそったりされたのは、高安国世夫妻だった。
高安さんは、京都大学のドイツ文学の助教授であり、私は人文科学研究所の助教授だったので、学問上のつながりはない。それでも、そのころの京大は、ひとつの小さい大学だった。戦争に負けたということが、この大学を小さいものと自分たちに思わせた。 本を借りるにも、大学図書館の索引箱でたしかめてから、ちがう学部の図書室にさがしに行くことがあった。バーコフの『美の尺度』が数学の図書室にあり、ペリーの『価値の一般理論』(哲学の本)が経済学部の図書室にあって、読まれることなく、そこに眠っていた。
小さい大学だから、工学部建築学科の西山卯三先生のとなりにすわることもあったし、経済学部の青山秀夫先生がなんとなく私の研究室に話しにくることもあった。記念祭のときに、明治時代の東洋的社会主義者小島祐馬先生が土佐から出てこられたのに出会ったことさえあった。
文学部ドイツ文学の高安さんが、夫人と一緒に私を夕食にさそうのは、それでも、めずらしいことだった。それは、高安さんの御子息のひとりが聾だったので、そのことを入り口として、聾の記号の世界について、夫妻ともに考えることが生活上の問題だったからだろう。私の話が、高安夫妻の参考になったとは思えない。しかし、言語以前の人間の記号について、私は考えていた。話題を共有することはできた。
夫妻ともに、短歌の結社の中心におられ、短歌には、言語を仲だちとして、言語の外の世界への気配をとらえようとする修練がある。「青磁社通信」六号に、
ヒトの語とひきかえにわれは失いし子が雀らに語りいることば 森尻理恵
があって、そういう修練が、家庭内の日常を、ひろく表現の問題として夫妻の前に置いたのだろう。
私は短歌を作らないので、結社の外にいたが、高安夫妻は、なくなられるまで、私に声をかけることを続けた。ドイツ語訳の歌集が送られてきて、そのとき、私ははじめて、ドイツ語に訳された短歌と、日本語として書かれた短歌とのちがいに、気づいた。ドイツ語では行分けとなるが、日本語として、短歌は一行で表現されるという本質的なちがい(短歌をつくる人にとっては自明なこと)が私に明らかになったのは、それ以来のことである。
その後御子息は、画家としてあざやかな世界をつくられ、その作品を見ることもできた。
やがて、「塔」を高安国世さんから受けつがれた永田和宏さんが、私の家の近くに住まれるようになり、私は、途で時として会うことを通して、永田さん御一家と近づきになった。
東京生まれの私としては、京都の町を背景とした、このつきあいは、あたらしい。あたらしいとは言っても、昭和二十四年以来、ここに住んでいるのだから、古いはずなのだが、それでも、私にとっては、まだあたらしい。
それは、十五歳で日本を離れて、一度、日本語が頭の中で消えたからである。満二十歳で日本に戻ったときは日米戦争の中であり、私は家族とともにいても、また軍隊の中にいても、どうかすることのできない自分を感じていた。その気分は、戦後も私の中に残っている。日本語に戻ってから六十二年たち、もはや英語をたくみにあやつることができるわけではないが、日本語に対する別のものという感じは、今も残っている。
自分が八十歳をこえて、もうろく語をあやつるようになってから、その中に日本語も英語も流れこむ。そのようにして人間の言語に達し、やがて、これもたくみにあやつれないところまでくると、人間とはちがう存在語に行きつく。こうして、一度断たれた日本語との関係は、断たれた痕跡を、私の中に保ちつづける。そういう予測をたてるのは、私がまだ、存在語の中に暮らしてはいないからだ。
存在語の気配に向かう短歌がある。
夕飯を呼びにゆきしがこれの世に夫と交わせし最後となりし 河野君江