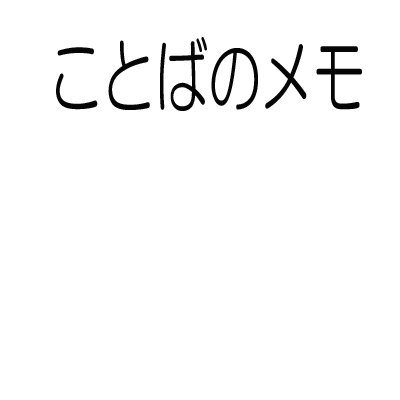きょうの高安国世の言葉より
『抒情と現実 今日の短歌 明日の短歌』(高安国世)という本が1956年に発行されました。塔短歌会の藤田千鶴さんが約1か月にわたってこの本から言葉を抜き出してブログに書いていました。
ここでは、この本のエッセンスとして藤田さんが選んだ高安国世の言葉をここに紹介します。
(藤田さんの許可は頂いています)
(1949.01.01)
誠実なるものはおのずからにして一つの新しさに到達する。
誠実とは自己自らに対して誠実であることである。
自己に対する誠実はおのづからまた自己の生きているその現実に対する誠実をも内に含むものだからである。
(1947.09.16 『高槻』第2巻第9号)
芸術に最も必要なものは個性である。個性のない芸術は本当の芸術ではない。
個性とはもちろん独りよがりの事ではない、個人的な癖や歪みのことではない。
それは最も純粋に個性的となるに従って、深い人間本質に連なり普遍的なものになるものだ。
(1947.09.16 『高槻』第2巻第9号)
一つの論を立てるのはよい。だが自縄自縛に陥らぬ闊達明敏さが必要である。
自ら規定したものに違わざらんとして些かでも自由を束縛し、真意をまげるに到れば不幸である。
実作は理論をどんどん破って進むべきものである。
論はむしろその時々の作者の決意を示すだけのものであり、従来の自己に対する一つの決算報告であるに過ぎない。
自己のあり方を確かめ、未来への決意を固めたならば、その用はもう果したのだ。
作者は、実はもうそこには居ないのである。
(1949.05.03)(『風物』(7)1949.07)
僕たちは受けついだ技術を持ち、新しい教養に立つて歌おう。
その点は自信を持つと共に更に更に努力する必要がある。
そうしてまだ躊らい模索している二十代の人々の間に入つて錬磨し合うことこそ我々に課せられた課題であり、
又自らを生かすゆえんであると思う。
(「都新聞」1949.03.27)
多くの現代作家の作よりも、偉大な人の余技によいのがあると仮定しても、 それは短詩そのものの性格ではなくて、それを扱う人間の問題である。 だから短詩を扱う者が、いわば短詩俳句の教養のみにとじこもることがまちがいなのであつて、 広く生活と文学とを勉強しなければならないことはいうまでもない。
(『日本短歌』1949.08)
生活感情という言葉に甘やかされてはならない。歌はやはり文学でなければならない。 作者はたとえ専門の歌人でなくても、毅然とした自己を持たねばならない。 芸術家としての気魄を持たねばならない。鋭い眼と高邁な心を養わねばならない。 もやもやとした現実の意識を明瞭に裁断し、些細な物の中に宿る意義と関連とを洞察する叡智を持たねばならない。
(1947.09.16 『高槻』第2巻第9号)
歌は又新しい退屈になろうとしている。ぼくは自分の問題としてこれを言おうとしているのである。 どうすればこれを切拓いて絶えず未開の分野へ突進み得るのか。一言に言えば個性であろう。 もつともつと自由に、周囲を顧慮せずに、隅つこの自分一人の工房に甘んじて、本気に歌を考え、 自分の問題をつきつめ、自分自身の表現を、言葉を生み出す工夫がなければならぬ。 本当のものが出来れば、それは自ら世間に通用する筈である。 縁の下の力持ちをも辞せない悠々として確乎たる信念を養わなければならぬ。 純乎とした、本当のものを生みたい。
(1947.09.16 『高槻』第2巻第9号)
短歌のような限られた形式では、一言一句の改革が重大問題であるにも拘らず、 模倣者は難なくこれを受入れて平板化することが容易である。 その背後にある精神の苦悶はその場合考えられずにしまう。 模倣するならもつとこの精神の根本を自己の問題として考え、 それと自己独立の精神との間に対決がなされなければならぬ。 そこに自己の精神の変容が徐々に行われるか、逆に自己の独立が確認されるはずである。 自己を回避した模倣など問題外である。
(1949.09.09)(『短歌研究』1949.11.12)
一つの理念から出発するのは本当の詩ではない。 我々は常識的な一つの観念を詩の形に現わそうとするのではなく、 やむにやまれず一つの物を、或る時の気持を歌い上げることによつて、そこに意味が成就されるのである。 あまりに意味を企図し、はじめから観念上の操作をもつて語句を秩序づけることは往々にして詩をとりにがす。 詩はもつと非合理的なものである。或いはもつと隠れた所における叡智の処理によつて成就される。
(『短歌研究』1950年11月)
芸術ではどんなに現実を再現しても現実そのものと等しくなることはあり得ない。 現実そのものの一部であれば、何も芸術と呼ばなくてもよいわけである。 現実と異なればこそ芸術と言うのであるから。(中略) それでは現実に合致することが、何故芸術の上でさほど意味があることなのか。 それはわれわれが現実の社会の生活に最も関心をもつことの必然のあらわれであり、 又芸術というものが現実に根を持たないと、人間と同様やはり生命の乏しいものになるのが普通だからである。
(1951.02『アララギ』2月号)
僕らは政治史や経済史のおもてにあらわれたとは別の、人間の魂の歴史を生きて、 ささやかな片隅の文学に遺すことを考えねばならぬ。 どんなに無力に弱々しく見えようとも、人間を抹殺しようとする有形無形の緒力に 圧迫され押しひしがれようとするぎりぎりの所で、曇りない眼と善意とを以て、 何が人間的であるかを語らねばならぬ。
(『短歌雑誌』第5巻第3号 1951.03)
意識して作つたようなものは「詩」ではあり得ない。 僕たちが自己の誠実を尽して生き、自己の能力を尽して歌を作る、 その時作られたものの上に来てとまる鳥が詩である。
(1951.05.21『短歌研究』第8巻第6号、1951.07)
一つの構えた心ではない柔軟な気持で、ひたひたと現実を感受すること、これが第一歩である。 それと芸術作品との間にある距離、今はそれを静かに考えて見なければならぬ時ではなかろうか。 その間の無反省がどれだけ多くの平板な日常短歌を産み出していることだろう。
(1951.05.21『短歌研究』第8巻第6号、1951.07)
「生きた胸を責めさいなむものが、石の中にあつては幸福を、歓喜を与える」
これがマイヤアのミケランジェロに得た教訓であつた。
苦痛である人生が芸術の中では浄められ、個々の姿は芸術の中へ死ぬことによつて永遠の生に高められる。
芸術ははかない人間の現身の自己否定であり新たな創造であつた。
マイヤアは歓喜してこの信条に生きた。
註:マイヤア・・・C.F.マイヤア 十九世紀のスイスの詩人
(『日本短歌』第20巻第9号 1951.10)
僕はよく、リルケを翻訳したり研究したりしながら、 歌の上では少しもそうした影響が認められないという不満をききます。 しかし僕は一体誰がリルケの影響などを直接受けて歌を作るという放れ業が出来るのか、 たとえ又出来たとしたら誰が果して面白く思うだろうかと不思議でなりません。 一寸した修辞上の真似などを軽々しく云々して面白がつたりすることは無意味だと思います。 根本的に生き方を考えるということがなくてはリルケは無縁です。 そして一人の詩人の根本的な生き方をそのまま自分のものにするなどということは既に詩人ではない証拠です。 詩人はその自ら置かれた位置において、誠実に自己の力の限りを尽して生活と伝統と教養との一切をごまかさずに、 自己の自然に耳を傾けて生きる謙虚さがなくてはならないと思うのです。
(『関西アララギ』12月号 1952.09.27)
ただ歌の面白さは素材とか生活とかからのみ来るのではない。 極めてこまかい言語の味わいが大きな比重を占めるものである。 そこに詩人としての精神が最も具体的にあらわれるものだからである。
(『関西アララギ』5月号 1953.03.21)
今日本当に充実した生活感情を持つには、どうしても知性の働きがなくてはかなわない。 しかしそれは単なる分析的論理的な知性ではなくて、 分析と同時に総合をおこなう直感の働きが重視されなければならない。 でないと歌が理窟になり、散文の一断片となり終るだろう。 我々は分析して割り出した論理的結論に衣裳をかぶせるのではない。 ふだんの思索が一瞬の体験に結晶して、その時生じる感動を抒情するのである。 考えつつ行動し、行動しつつ考える所以である。思想ばかりの所にも、行動ばかりの所にも文学はない。
(『詩学』第5巻第7号 1950.08)
徐々に徐々に、何が蓄えられてゆくと言うのであろうか。 一つ一つの体験を今僕はうたう気になれない。何か口に出して言えば毀れてしまうような印象が、 心の底の方でしずかに醸酵しているのでもあろうか。
(1951.12.24『関西アララギ』1952年 3・4・5月号)
芸術や詩というものは、もうその起こつた時からして矛盾を含んでいると言うことが出来る、 即ち、自然のままでは芸術ではない、自然に何物かを加え或いは変革することによつて芸術が生じるのである。 詩においては殊に、言語というものが既に自然をはなれた人間独自のものであり、 言語を用いて或事を言う時には既にそこに論理が入り、抽象が入り、物事は整理され、多くの事柄が切り棄てられる。
(1951.12.24『関西アララギ』1952年 3・4・5月号)
詩はむしろ最高度にこの機能を発揮して徹底的に無駄を棄てることによつて、 かえつて元の根源的現象を捉え、自然のリズムを生かそうとする人為的作業である。
(1951.12.24『関西アララギ』1952年 3・4・5月号)
抒情詩は彫刻のような純粋な造形美術ではない。ただ無暗に物を形作るだけが抒情詩の造形ではない。 如何に技巧が鮮かな描写であつても、魂のない人形のような作品をいくら作つても仕方がない。
(1951.12.24『関西アララギ』1952年 3・4・5月号)
最も個性的であればこそまた普遍的な生のシンボルとなるもの。とすると、 万葉集の相聞歌や挽歌を私は思い出すが、ああいうものを読むと 直ちに生命の核心にとび込んだような心のゆらぎを覚え、 限りないあこがれと、ひそかな甘美な充足とを体験するのである。 しかし、どれだけ私は作者について知つているであろうか。 極端に言えば、作者は誰であつてもいいのである。 抒情詩などそれでいいのかも知れない。或いは芸術品はすべてそうなのかも知れない。 目的はそれを鑑賞する人々の心に、その時実現する言うに言われぬ感動があれば足りる。
(1951.12.24『関西アララギ』1952年 3・4・5月号)
人それぞれに今はみずからの生き方を持たねばならない。 みずからの中に持つ大切なものを如何にして守り、如何にして育てて行くか。 日常に於けるそうしたささやかな苦闘や祈願こそ思想と呼ばるべきではないか。
(1951.12.24『関西アララギ』1952年 3・4・5月号)
鍛錬道から倫理的な臭いを消せば、芸術製作にはやはり鍛錬が必要だということになる。 ただ師法にのつとつて年期を入れさえすればよいという意味ではない。 借り物の思想やごま化しの表面的写実ではどうにもならないものが芸術には在るということである。
(1951.12.24『関西アララギ』1952年 3・4・5月号)
哲学大系のような、出来上つた思想をのみ思想というのは当らない。 芸術における思想とはもつと個人的な、血の温味のかよつた隠微な、呼吸のようなものであつてよい。 しかし先に述べたように現代の芸術から受ける感動は単に「美」ではなくて、美プラス何物かである。 その何物かはやはり「真」であり、真であればこそ「新」である何物かである。
(1951.12.24『関西アララギ』1952年 3・4・5月号)
ローベルト・クルチウスが「プルースト論」で言うように芸術作品とは、 「新しい精神的風景に向つてひろげられた一つの窓」でなければならない。 即ち一つの新しい真実の発見でなければならない。芸術作品とは最も具体的感覚的思想ということになる。 分析的論理的思想というよりは、直感的総合的思想である。
(1951.12.24『関西アララギ』1952年 3・4・5月号)
彼(リルケ)の中期の、一見われらの写生に通じる「物象」の詩も、 幸福な時代の、主観客観の融け合つた無邪気な状態からおのずと歌い出したものではなくて、 カロッサが鋭く見抜いて恐れたように、大切な生命の何物かを犠牲にし、 生命の流れを一時中断するような、極度の集中によつてかち得たものであつて、 一見そこには何の思想も苦悶もないかの如くであつても、 実は激しい精神的抵抗と祈願との所産である。
(『関西アララギ』5月号 1953.03.21)
歌の技巧や歌の言葉だけでは足りないものがあり、歌のことばかり一日中考えていることが
必ずしも歌のプラスになるとは限らないことを考えねばならない。(中略)
むしろ平ぜいの生活をせい一ぱいに生きていることが大切だ。これは一見矛盾した言い方だが、
現代に生きる歌人は、この困難な課題を負つていると言わなければならない。
(1949.09.09)(『短歌研究』1949.11.12)
我々はこれから作家を批判するのに先ず詩であるかどうか、
作者が詩的衝動をもつて作つているかどうかを考えるべきだろう。
一句一句を?えて言うのはそれからの話である。(中略)
往々にして我々は表現技術上の従来の自己の方法に逆らうものに反撥してしまつて、
その作者に詩的衝動があつても問題にせず、これを攻撃することが多い。
殊に従来の結社的意識がこれを助けている。
我々は一応、作家を結社の光背から取りのけて、一個独立の詩人としてみなければなるまい。
(『都新聞』1949.03.27)
批評家または読者は、今日の進んだ短詩をどの程度勉強しているであろうか。 体あたり的に短詩の限界にぶつかつて行こうとする僕たちから見れば、 既製の「短歌的なるもの」という概念のとりこになつて、動こうとしない局外者の批判はのん気すぎるのである。
(1951.12.24『関西アララギ』1952年 3・4・5月号)
大伴家持の、
うらうらに照れる春日にひばりあがり心かなしも独りし思へば
これは人麿の宇治河の歌と同様、或いは更に完全に独詠の歌である。
周囲から切り離された自己の領域にとじこもつている。そして人麿が河波と自己とを同一化し得たのに対して、
家持では春日と雲雀とを背景として「心かなし」と自らの自我の孤独が前面に出て来ている。
内省的とまでは行かないにしても、もはやそれは外界に没入して自己を自然の中に生かし、
自然が自己の中に呼吸するという態度ではない。ここに個別化の進んだ時代がまざまざと感じ取れるのではなかろうか。