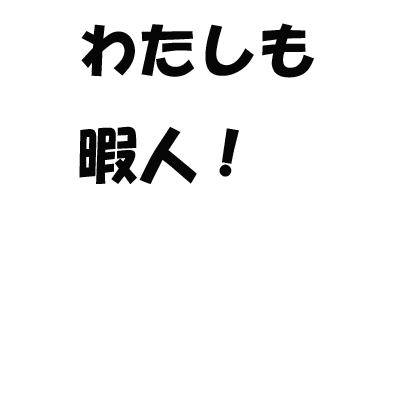名歌集探訪(栗木京子)に取り上げられた歌集
高安国世『真実』(1949)
限りなくみじめなるをば重ねつつ湧きくる力たのめりひとり
見とほしになりし山辺をふりさけぬ我が生ひ立ちの家の焼跡
この位置にこの本らある安けさよ去年の一昨年の夜ふけの友よ
ひたすらに子を教へ子を死なしめてそれより子らを我が目守るのみ
短編ひとつ訳し終へたる安らぎに昼少し前の図書館を出づ
ひたぶるに夜の構内を貨車過ぐる長き轟きの中に立ちたり
男として仕事したしと言ふさへにいたいたしき迄に妻を傷つく
我がジャケツのポケットに手を差し入れて物言はぬ子の寄添ひ歩む
八百屋にも我は来慣れてためらはず嵩ありて安き間引き菜を買ふ
人参に並ぶ一畝は子のために蒔きしコスモス時早く咲く
大野誠夫『薔薇祭』(1951)
中城ふみ子『乳房喪失』(1954)
森岡貞香『白蛾』(1953)
河野愛子『木の間の道』(1955)
尾崎左永子『さるびあ街』(1957)
きざし来る悲しみに似て硝子戸にをりをり触るる雪の音する
戦争に失ひしもののひとつにてリボンの長き麦藁帽子
ゆくりなく放たれし赤き風船が雲に近づきながらかがやく
人の声なべて消さるる地下鉄の轟音の中に安らぎゐたり
花終ふるサルビアの朱傾きて日にかわきゐる公園に来つ
冬の苺匙に圧しをり別離よりつづきて永きわが孤りの喪
真鍋美恵子『玻璃』(1959)
安永蕗子『魚愁』(1962)
つきぬけて虚しき空と思ふとき燃え殻のごとき雪が落ちくる
ひたすらに町の在り処どを消してゆく霧湧きながら冬の紫
ひかりつつ暇ひまなき雨に応へゐる草の限りの声が聴きたし
舟のかたち成りゆくまでに削りたる木屑を踏みて島の春逝く
砂なかに双手埋めて温かしはかなきことも海に来てする
やはらかに小指朱肉に押しつけて心かすかにほめく時あり
馬場あき子『無限花序』(1969)
シュプレヒコール声嗄れて夏の街ゆけり腕くみて信じあうほかになく
片方の赤きサンダル浮べつつ運河はまこと海に到るや
子を欲るはわれへのくさり子を欲りて愛ためすなれ五月のすもも
ひとつずつ指の死にゆく怖れ湧きいま戦後にてまたは戦前
村木道彦『天唇』(1973)
岡井隆『鵞卵亭』(1975)
優しさははづかしきかな捲きあがる水の裾から言葉を起こし
カフカとは対話せざりき若ければそれだけで虹それだけで毒
歳月の熟れゆく房のうつくしき他人事(ひとごと)とのみ見つる限りは
労働ののち寂かなる夕(よひ)は果つあせらず生きむ殺さるるまで
沈黙のもたらす遠き結実のあやふけれども雨(あま)ごもりたる
葉擦れ雨音ふたたび生きて何せむと病む声は告ぐ吾(あ)もしか思ふ
ホメロスを読まばや春の潮騒のとどろく窓ゆ光あつめて
からたちの萌黄といへどその暗くしづめるいろに花は順(したが)ふ
子殺しにちかしとぞいふ一語をもななめ書きして手帖古りたれ
原子炉の火ともしごろを魔女ひとり膝に抑へてたのしむわれは
春に居てむしろ恋ほしむ冬木立簡浄の枝没日(いりひ)を囲ふ
薔薇抱いて湯に沈むときあふれたるかなしき音を人知るなゆめ
あぢさゐの濃きは淡きにたぐへつつ死への一すぢの過密花あはれ
労働が救ふときけば匂ふなあ嘘偽(うそ)がほのかに 蒼き雪降り
歌はただ此の世の外の五位の声端的にいま結語を言へば
永田和宏『メビウスの地平』(1975)
わが愛の栖といえばかたき胸に耳あてており いま海進期
肩車にはじめて海を見し日よりなべてことばは逆光に顕つ
きみに逢う以前のぼくに遭いたくて海へのバスに揺られていたり
ひとひらのレモンをきみは とおい昼の花火のようにまわしていたが
きまぐれに抱きあげてみる きみに棲む炎の重さを測るかたちに
駆けてくる髪の速度を受けとめてわが胸青き地平をなせり
草に切れし指を吸いつつ帰り来れば叫びたきまでわが身は浄し
高野公彦『汽水の光』(1976)
人間に生きつつ或る夜さびしくて鏡のなかに我を呼び出す
雨の夜の坂のぼりつめ君が見し最後のひかり我は思ひぬ
子を呼びに出でてゆきたる妻のこゑ方位感なくきこゆる日暮
ふるさとの奥処といはむくろぐろと藻が襤褸なす冬潮の底
あゆみきてわが影佇てばあさがほの花々の裡みづのこゑする
阿木津英『紫木蓮まで・風舌』(1980)
島田修二『渚の日日』(1984)
ひとり行く北品川の狭き路地ほうせんか咲き世の中の事
運動をはじめし独楽が定めなく静かに位置を移しつつあり
傘の上にさわがしく雨音のして色沈みたる枯れ野ありにき
うしろより来て眼を塞ぐ人の手の柔らかければ何思いけん
根気よく電話が人を呼んでいるこの白昼を棟(おうち)散りたる
この谷戸はちらりほらりと梅咲いて明け方の雨道を濡らせり
寒々と更けゆく冬の夜がある四角な部屋に凧をつるして
このあたり栗の木のなき筈なのに日々の落ち葉に栗の葉混じる
忍ぶ川ほそき流れは芹青きところにきたり音のせせらぐ
膝かかえ柱によりていたるとき夕日ふるえて軒を離れつ
佐佐木幸綱『瀧の時間』(1993)
高安やす子『樹下』
入手不能